福祉用具貸与事業
福祉用具貸与の対象は「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」等13品目で、要介護度に応じて貸与できるものが異なります。
要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。
また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。

利用者負担
※福祉用具貸与に係る費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)を利用者が負担します。
※費用は対象品目によって異なります。また、要介護度別に1ヵ月間の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合 せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。
福祉用具事業者として指定を受けるには、以下の人員基準、設備基準、運営基準をクリアている必要があります。
なお、介護予防福祉用具貸与と福祉用具貸与とでは運営基準が若干異なっています。
①法人格を有している。
②登記上の事業目的に訪問介護事業を行うことが明記されている。
③福祉用具専門相談員
(資格要件)
・介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、
社会福祉士 介護職員基礎研修修了者、介護員養成研修1級・2級課程修了者
・福祉用具専門相談員指定講習の修了者
・都道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習に相当すると認める講習の修了者
(配置基準)
常勤換算で2人以上配置されていること
④管理者
(資格要件) なし
(配置基準)
専らその職務に従事する常勤の者1名
⑤事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画が確保されている。
・事務室…職員、設備備品が収容できる広さを確保すること
・相談室…2名以上で利用可能であり、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないようプライバシー保護に配慮した
もので、利用者申し込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保しているものであること
・福祉用具貸与事業を行うために必要な設備、備品(机、いす、パソコン、鍵付き書庫等。)
⑥福祉用具の保管のために必要な設備及び器材。
・清潔であること。
・既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を、保管室を別にするなどして、明確に区分することが可能で あること。
⑦福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材 。
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

指定申請手続きに必要な書類
*各都道府県や市によって必要書類は若干異なってきます
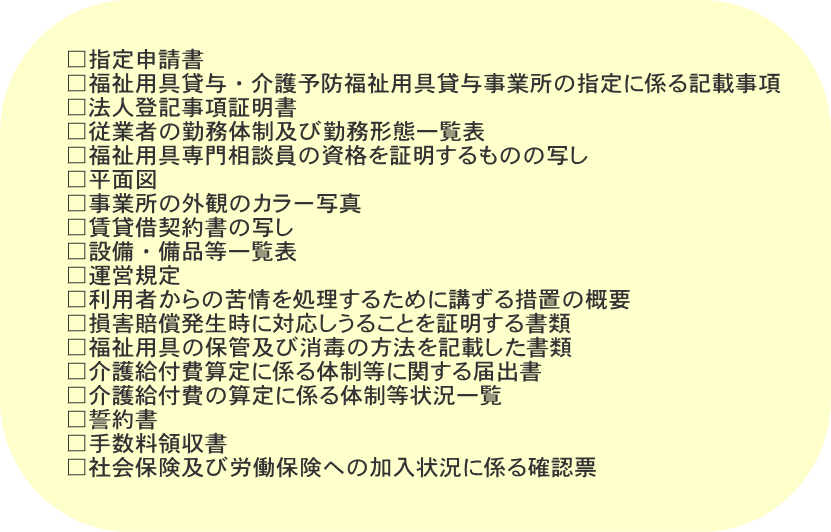
*指定申請手数料については、都道府県や市のホームページでご確認ください。
以上、指定を受けるためには、役所で事前相談を行った上で、煩雑な書類一式を作成していかなけれなりません。
時間に余裕があり、書類作成に手慣れた方であれば、ご自身での手続きも可能ですが、介護・障害福祉事業の立ち上げでは申請手続き以外にも事業開始前にしなければならないことが数多くあります。指定申請手続きをお任せいただくことで、その時間を経営者にしかできない本業に充てることが可能となります。
当事務所では開業立ち上げから以後の労務管理までワンストップでお任せいただけます。